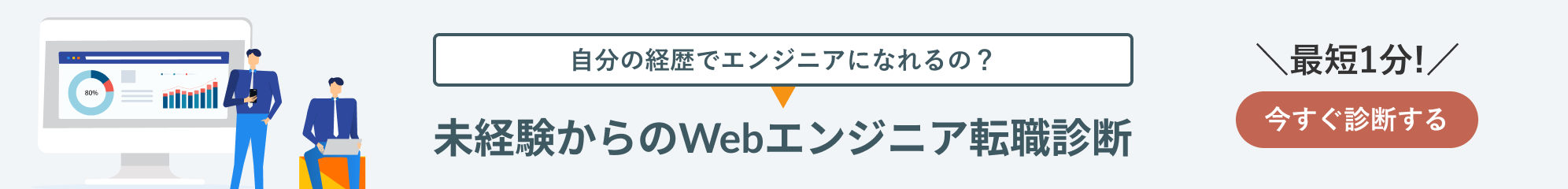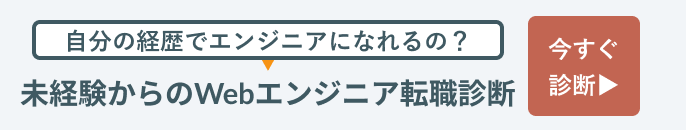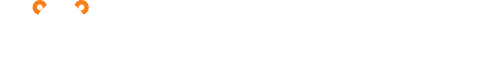近年、「AIエンジニアはいらない」「AIによってエンジニアの仕事がなくなる」といった声を耳にすることがあります。特にChatGPTなど生成AIの登場以降、「AIが自動でプログラムを書いてくれるなら、将来エンジニアは不要になるのでは?」と不安に感じる若手エンジニアもいるかもしれません。しかし、それは大きな誤解です。結論から言えば、「AIでエンジニアは終わる」というのはウソであり、むしろAI時代においてエンジニアの需要は高まっています。本記事では、その理由を論理的な根拠や事例とともに解説し、AI時代を生き抜くヒントをお伝えします。
エンジニアがAI時代にも必要とされる主な理由:
-
AIが進歩しても、人が生活のために働く必要はなくならない – AIがどれだけ発達しても、人間が「稼がないと生きていけない」現実は変わりません。
-
収入を得る手段はAIを活用する仕事へシフトしている – AIで仕事の効率が爆発的に向上する時代では、AIを使いこなせる人ほど稼げるようになっています。
-
AIを支えるシステムやサービスを作るエンジニアが不可欠 – AIそのものを社会で役立てるには、それを実装するインフラや仕組みを作るエンジニアが必要です。
これらのポイントについて、以下で詳しく見ていきましょう。
ショート動画でも解説しております!
https://youtube.com/shorts/ItaD_6qLYak?feature=shared
理由1:AIが進歩しても「働く理由」は消えない
AIの進歩で仕事が自動化されても、人間が働かなくてよくなるわけではありません。なぜなら、どれだけ技術が便利になっても、私たちが生活していくためにはお金を稼ぐ必要があるからです。

AIがどれだけ便利になっても、生活費はかかりますし、人間の“働く理由”が完全になくなるわけではありません(上のスライドが示す通り)。要するに、いくらAIが普及しても「収入を得る」という人間の根本的な目的は変わらないということです。
現代の社会システムでは、仕事を通じて収入を得て生活するのが基本です。仮にAIによって多くの業務が自動化されても、人々が収入を得る手段自体がなくなることはありません。むしろ、新しい技術が登場する度に「働き方」が変化してきた歴史があります。産業革命で機械が登場したときも、人間は機械に仕事を奪われたのではなく、新たな仕事を見つけ出し適応してきました。同様に、AI時代においても人間が働く理由そのものが消えることはなく、形を変えて働き続けると考えられます。
もちろん将来的にAIがもたらす効率化によって労働環境は大きく変化するでしょう。しかし、仮にAIが高度に発達しても、誰もが働かずに生きていける社会(例えばベーシックインカムが完全実現した世界)が訪れない限り、「生計を立てるために働く」という人間の営み自体は存続します。要は、AIが便利になって私たちの生活が楽になっても、人は何らかの形で価値を生み出し対価を得る必要があるのです。
理由2:AIを使いこなせる人ほど稼げる時代へ
次に、収入を得る手段そのものがAIの登場によって変わりつつある点に注目しましょう。

実際、AIの普及は「仕事がなくなる」どころか新たな仕事を生み出す要因にもなっています。世界経済フォーラムの報告によれば、2025年までにAIと自動化によって消える仕事が約8500万ある一方で、それ以上にあたる約9700万の新たな仕事が創出されると予測されています。つまり、AIによって一時的に一部の職種は減少しても、それを上回るペースでAI時代に適応した新しい職種や雇用機会が生まれていくということです。特にテクノロジー業界では、AI・機械学習のスペシャリストやデータアナリストといった役割が今後数年で30~40%も需要増加すると予測されています。これらはまさにAIを使いこなす人材であり、そうしたスキルを持つ人には多くの引き合いがあるのです。
では逆に、「AIを使いこなせない人」はどうなるでしょうか?極端に言えば、単純作業しかできずAIでも代替できてしまう人こそが危ういですが、それをもって「エンジニア全体が不要になる」という主張は飛躍しすぎです。優秀なエンジニアであればAIを積極的に駆使することでさらに高付加価値な仕事を生み出せるだけであり、AI時代においてますます重宝される存在になります。実際、AIを上手に使って短期間でプロジェクトを回せるエンジニアや、業務にAIを組み込んで生産性を劇的に高められる人材は、これからの職場で圧倒的に有利になることは間違いありません。
要するに、これからの時代は「AIに使われるのではなく、AIを使いこなせる人」が勝つ時代です。AIを恐れて排除しようとするのではなく、自分のスキルセットにAIを取り入れて武器とする人こそが、今後大きな価値を生み出し高い収入を得られるでしょう。
理由3:AIを活用するシステムを作るエンジニアが不可欠
最後に、AIそのものを社会で役立てるためには「AIを使ったシステム」を作るエンジニアの存在が不可欠である点を強調します。

例えば、最新のAIモデルが登場しても、それを使ったアプリケーションやサービスを設計し、既存の業務フローに統合し、動かすのはエンジニアの仕事です。AIシステムの開発から実装、テスト、デプロイ、運用に至るまで、ソフトウェアエンジニアリングの専門知識が求められるのは間違いありません。AIが自動でコード生成できる部分もありますが、どのような仕様で何を作るかを決める要件定義や、レガシーシステムを含む複雑な環境への統合作業などは人間の経験と洞察が必要で、機械任せにできるものではないのです。実際、「AIに全部やらせればいい」と安易に考える人ほど、現場の泥臭さやシステム開発の複雑さを理解していないとも指摘されています。現実のプロジェクトでは人間同士の調整や最終判断を下すリーダーシップも不可欠であり、そうした役割を果たすエンジニアやマネージャーは今後も必要とされます。
さらに、日本の企業動向を見ると、AIやDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進できる技術人材の不足が深刻です。によれば、企業の41.8%が「DXに関わる人材の不足」を課題に挙げており、まさにAIを活用できるエンジニアが足りていない状況が浮き彫りになっています。AI技術を導入したくても、それを社内で扱える人がいなければ実現できません。このことは裏を返せば、AI時代に精通したエンジニアには引く手数多のニーズがあるということです。AIを扱えるエンジニアは、企業のデジタル変革を支える「インフラ担当」として今後ますます重宝されるでしょう。
総じて、AIの発展はエンジニアから仕事を奪うどころか、エンジニアの役割を進化させ重要性を高めています。にもある通り、「AIがエンジニアを駆逐する」というのは机上の空論であり、現実の現場では生身のエンジニアによる知恵や責任ある判断が不可欠です。若いエンジニアの皆さんに伝えたいのは、AI時代を悲観する必要は全くないということです。大切なのは、AIに取って代わられるような単純作業に甘んじるのではなく、AIを自らの力に変えて活用できるエンジニアになることです。技術の進歩に合わせて学び続ける姿勢さえあれば、むしろこれからの方がエンジニアには面白いチャンスが広がっています。AIを味方につけたエンジニアこそが、これからの時代に価値を創造し続ける主役となるでしょう。
まとめ: 「AIエンジニアいらない」は誤解であり、現実にはAI時代にエンジニアはますます必要とされています。人々が働く理由が消えない以上、仕事の形はAIと共に進化し、新たなチャンスが生まれます。これからはAIを使える人が強く、AIを活用できるエンジニアほど市場価値が高まる時代です。AIは脅威ではなく道具です。ぜひ恐れずに積極的にAIスキルを身につけて、時代の先頭を走るエンジニアを目指してください。それが、高収入を得て活躍し続けるエンジニア人生につながるはずです。